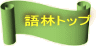9月12日(日)「はじめての二胡」というイベントを開きました。
講師は以前、語林教室の生徒さんで、NPO日本二胡振興事務局に所属する小沼恭子さんです。サブ講師に同会の秋田さんもいらしてくださいました。
参加者が多かったため、4~5人ずつ前半と後半に分け、全員に二胡がわたるようにしました。
二胡の歴史
まず二胡の歴史を簡単にご説明いただきました。もともともアラビアが起源です。西に伝わってバイオリンとなり、シルクロードを経由して東に伝わって二胡になりました。中国で宮廷の楽器に入れられなかったので日本には伝わりませんでした。歴史に始めて登場するのは唐代。劇音楽の伴奏する楽器でしたが、1900年代初め、劉天華という人が旋律を引く楽器として大学に二胡の専門学科を作りました。ここで初めて日の目をみたといえます。文革後、多くの二胡奏者が海外に流出し、日本にも来ました。それで次第に海外でも定着するようになりました。
ポイントは二胡を持つ姿勢
小沼先生が二胡を軽く弾くと、小さな楽器から出た音とは思えない大きな音に一同びっくり。
いよいよ演奏のレッスン開始!最初は二胡の持ち方から。左手で二胡を持ちます。そして左足の付け根に胴を置き、左足は少し前に出します。安定させるために胴の背を自分のお腹にもくっつけていいとのこと。いい音はお腹に響くそうです。棹は前方に傾けますが、そのとき若干左側に倒します。そして右手に弓をお箸を持つように持ちます。弓はいつも同じところを弾くので、下部に固定させて弦と直角に。
いよいよ音を出す
音を出すには、腕を左右に水平に動かします。肘から下だけを動かすのではなく、肩から手首まで動かすという弾き方を小沼先生が示しますが、その動きの滑らかなこと!そのポーズを保ちながら内弦と外弦を弾く練習をします。そうなのです、「二胡」というだけあって、2本の弦があり、内側の弦は低音、外側の弦は高音を奏でるしくみです。左手の先で弦の上部を押さえ、音階を作ります。内側の弦でドからファ、外側の弦でソからオクターブ高いドが左指の押さえ方によって出すことができました。とうとう約40分の間にドレミファソラシドが弾けるようになりました!意外に早い!
目標達成!
そして残り10分で『きらきら星』に取り掛かりました。そして何と全員で『きらきら星』が弾けるようになりました!
丁寧なフォロー
演奏が終わってからも小沼先生は一人一人の姿勢を見たり、音をチェックしたり、質問に答えてくださいました。
受講者「ギコギコいう音がすごくいやなんですけど」
先生「いやですよね。(手首でなく)肘から弾くようにすればいいですよ」
受講者「二胡はいくらくらいしますか」
先生「安いのは3万円くらいです」
受講者「3万円の出費が必要かも」
「腕の付け根とか肩とか、痛くなっちゃうかもしれません」と普段、楽器を触らない受講者を気遣ってくれる優しい小沼先生の最後の一言に何だかほっとしました。